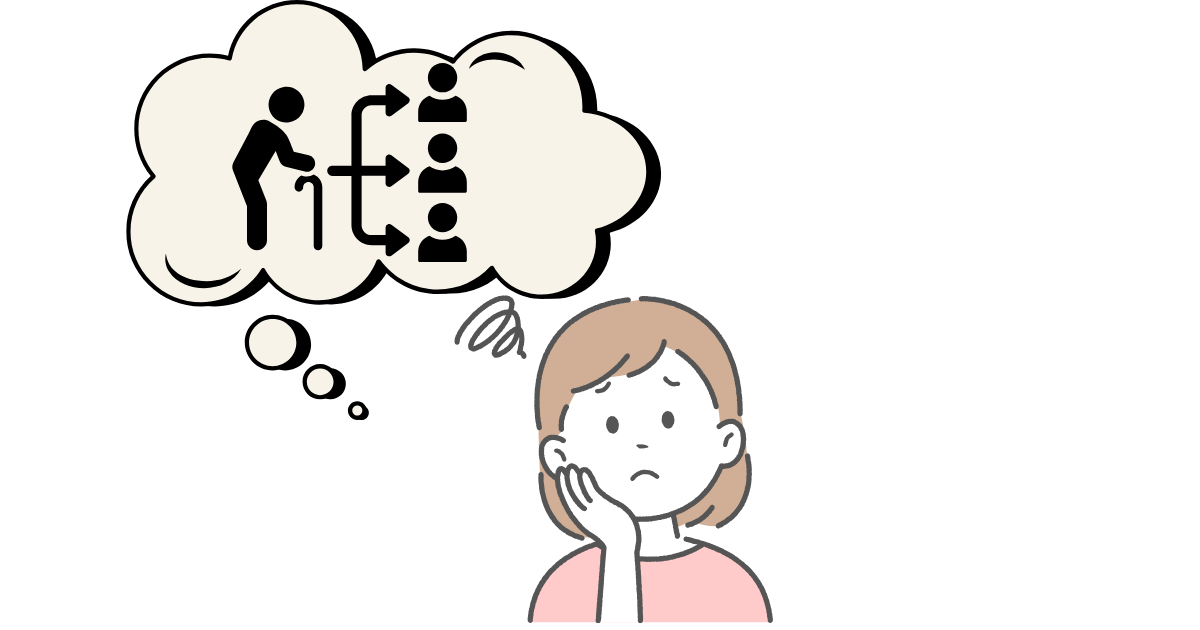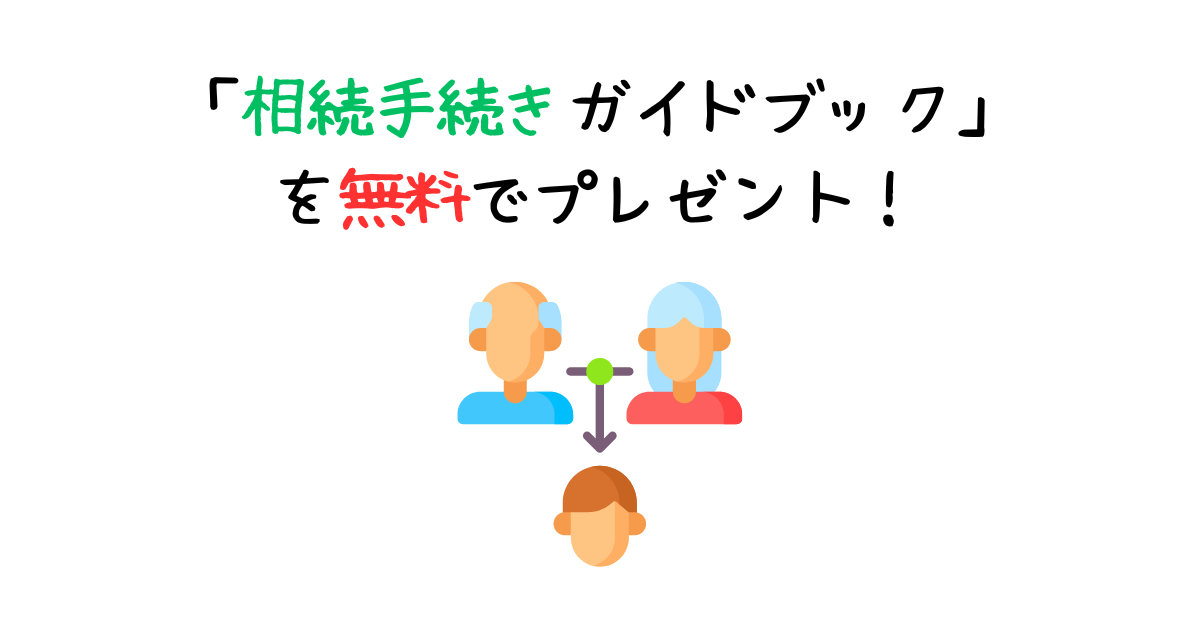TEL 0532-62-5034
受付時間9:00~18:00
(土日祝日は要事前予約)

(所属会)愛知県司法書士会 会員番号2133・簡裁訴訟代理等関係業務 認定番号第1801503号・一般社団法人日本財産管理協会
(経歴)愛知県豊橋市、太田合同事務所代表司法書士。2018年司法書士登録後、司法書士法人で業務に従事し、2022年太田合同事務所を開設。『地域・思いやり✖︎webオンライン密着✖︎充実した情報』をモットーに、司法書士業務と共にWebメディア運営にも取り組んでいる。
(趣味)サッカー観戦(セリエA、プレミア、Jリーグ、ゲームでフットボールマネージャー)、子供と遊ぶこと(娘が2人います)
ご家族が亡くなり、お葬式などが一段落して、少しづつ事務手続きのようなものを始めなければ・・・と考えている方も多いのではないでしょうか。
そもそも相続手続きとは何をすることでしょうか?
相続手続きに明確な定義があるわけではありませんが、基本的には不動産の名義変更(相続登記)、税申告(相続税の申告)、金融機関口座の解約などを指します。
亡くなった方の資産を相続人に移したり、それによって行政などの公的機関に届出などを出すことと言えます。
手続きを始めなければいけないと思いつつ、なかなか踏み出せないという方もいるかと思います。
手続きに踏み出せない理由
- 難しそうで調べるのが面倒
- 他の相続人と話し合いをするのも面倒
- そもそも何から始めればいいのかわからない
- 普段忙しくて調べたりする時間がない
まもなく長期連休に入るという方も多いのではないでしょうか。
親族家族が一堂に会するということもあるかと思います。
長期連休に入る前に、自分達が行う相続手続きの大まかな把握をして、スムーズに親族と話を出来るようにしておきましょう。
最初に確認すべきこと
相続手続きを始めるにあたって、いくつかの確認事項があります。
手続き前に確認しておくことで、後々の手続きがより楽になりますので、しっかりと確認をしてからスタートしていきましょう。
まずは誰が相続人か確認しよう(戸籍集めのポイント)
相続手続きをするのであれば、誰が法律上の相続人なのか確認をしておく必要があります。
民法で法律上の相続人は決められていますので、それに従って決まります。
民法 第887条 (一部省略)
被相続人の子は、相続人となる。
民法 第889条 (一部省略)
次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
民法 第890条 (一部省略)
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。
第一順位 配偶者と子供
第二順位 配偶者と直系尊属(父母、祖父母)
第三順位 配偶者と兄弟姉妹
相続人は戸籍を取寄せて内容を確認して、確定させることになります。
法律上の親族の関係性は、戸籍で証明するためです。
相続登記などで必要な戸籍は複数種類あります。
最近では、配偶者や子供であれば亡くなった人の戸籍を一括取得できる「戸籍の広域交付制度」という便利な制度も始まっていますので、それらの制度を利用しながら、戸籍を集めたり、自分で手配する時間がないようであれば、司法書士などの法律専門職に依頼することで、代わりに取寄せをしてくれます。
遺言書はある?ない?調べる方法
相続手続きを行う場合、まず初めに確認したいこととして、遺言書があるか?ないか?です。
遺言書の有無によってその後の相続手続きで使用する必要書類が変わってきますので、そこの確認が出発点になります。
遺言書があると、遺産分割協議書が無くても手続きが出来ますので、もちろん状況にもよりますが、比較的書類集めなどに苦労せずに進めることができます。
遺言書があるかどうかは、遺言書の種類によって調べられるものと調べられないものがあります。
公正証書遺言
公正証書遺言の遺言検索システムを利用して遺言書の存在と内容を確認できます。
検索が出来るのは、相続発生後は法定相続人、受遺者、遺言執行者などの利害関係人です。
(公証役場HP 遺言書検索システム)
自筆証書遺言
原則的に自筆証書遺言の場合には、調査をする方法はありません。
よく遺言書が保管されやすい場所として、親族に預けているとか、銀行などの貸金庫にあるなどです。
ただ、自筆証書遺言保管制度を利用している場合には、保管している遺言書を閲覧することが出来ますので、法務局で調査をすることができます。
閲覧が出来るのは、相続人、受遺者・遺言執行者などの人です。
(法務省HP 自筆証書遺言保管制度)
財産の内容をある程度把握する
相続手続きを行ううえで、財産の内容(種類や額)把握しましょう。
把握が出来ていなければ必要な手続きやかかる費用などはわかりません。
詳細にわからなくても最終的には専門家に確認してもらえば、問題ありませんのである程度は把握をしている状態にしましょう。
相続登記とは?しないとどうなるの?
相続登記とは簡単に言えば、亡くなったひとの名義になっている不動産をその相続人の名義に変更する手続きです。相続登記について詳しく解説した記事がありますので、そちらをご覧ください。
2024年に相続登記の義務化が始まったことに伴い、相続登記を行わないと様々なリスクがあります。相続登記の義務化などについて解説した記事がありますので、そちらをご覧ください。

太田徹
2024年の相続登記義務化によって、罰則規定ができましたので、登記は行うようにしましょう。当事務所では2024年以降、相続登記のご相談は増えている印象です。
相続登記に必要な書類と流れ
相続登記では一般的に以下のような書類が必要になります。
必要書類リスト
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍一式
- 被相続人の死亡時の住所がわかる住民票や戸籍附票
- 法定相続人の戸籍
- 登記名義人の住民票
- 法定相続人の印鑑証明書
- 遺産分割協議書や遺言書
- 不動産の固定資産税評価額がわかる資料
手続きのおおまかな流れ
- 不動産と相続人の調査
亡くなった人がお持ちだった相続不動産を確認する必要があります。
法定相続人を確認するため、戸籍などを取寄せて調査をします。
ご自分で行うのが難しい方は、専門家へ依頼すれば確認してくれます。 - 話し合い
遺言書がある場合には別ですが、遺言書がなければ、遺産分割協議という相続人同士での話し合いをする必要があります。この話し合いで、誰がどの資産を引き継ぐのか決める必要があります。
- 書類押印と登記申請
2で話した内容をもとに、遺産分割協議書や司法書士へ依頼する場合には委任状などを作成して、相続人から署名と押印をもらいます。書類が揃うと1で取寄せた戸籍などと一緒に法務局に提出します。
- 登記完了とお渡し
時期や法務局にもよりますが、1週間から10日ほどで登記の審査が完了し、新しい名義人の権利証(登記識別情報通知)が発行されます。専門家へ依頼すれば法務局での受け取りや書類のまとめなどは行ってくれます。
兄弟で話し合うときのポイント
上述の通り、遺言書がなければ遺産分割協議書を作成する必要があり、兄弟など相続人間での話し合いは不可欠です。話し合いの際のポイントとしてはいくつかあります。
主に以下のようなことに注意してみてはいかがでしょうか。
- 相続資産の全てを把握したうえで話し合いの機会を持つ
- 結婚をしている人は配偶者を話し合いに入れない、入れさせない
- わからないことが多いなら、なるべく相続人全員で専門家のところへ相談にいく
- 互いに譲り合う気持ちを忘れずに

太田徹
当事務所でも過去には、相続人ではない相続人の配偶者が話に介入したことで、話がこじれてしまったケースがあります。そのような場合には、法定相続人だけでの話し合いを強く推奨しています。
よくある不安・悩みとその対処法
Q遠方に住む兄弟と連絡がとりにくいのですが・・・
まったく連絡が取れない場合には話が変わりますが、ある程度連絡がとれる関係性なのであれば、司法書士などの専門家に依頼すれば、書類のやり取りなどは行ってくれるかと思います。
Q相続放棄を考えている弟がいるのですが
相続放棄は家庭裁判所で正式な手続きが必要になります。また期限(自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内)がありますので、期限内に行わなければいけません。ちゃっと相続では、相続放棄のご相談も司法書士が対応しますのでお問い合わせください。
Q自分1人で進めていいのかわからないのですが・・・
上述の通り、法定相続人同士での話し合いは必要になりますので、話し合いを進めたうえで代表の方おひとりが専門家などに相談をして手続きを進めていくというケースはよくあります。
司法書士に相談するメリットと費用
相続登記は司法書士などの専門家へ依頼しなくても、自分で行うこともできます。
司法書士へ相続登記を依頼するメリットはなんでしょうか。
具体的には以下のようなメリットがあります。
- 安心確実で、法的リスクなどを考慮して相談に応じてくれる
- 手続きを行う手間が省ける
- 自分で行うよりも迅速に手続きを行ってくれる

太田徹
特に普段お仕事をされているような人は、ご自分で手続きをする余裕はないかと思います。そのような方はメリットがあるのではないでしょうか。
司法書士ができること
司法書士に相続登記を依頼した場合には、ほとんどのことは行ってくれます。
手続きで必要な書類なども戸籍も含めて取寄せてくれますし、遺産分割協議書も作成してくれます。
当然、法務局への手続き申請や書類の受け渡しなども行ってくれます。
依頼者自身が行うこととしては、印鑑証明書の取り寄せや遺産分割協議書に署名押印を行っていただくなどになります。
費用の目安
司法書士の報酬は現在、自由報酬制ですので、事務所により費用は異なりますが、土地1筆建物1棟の一般的な居宅と土地の相続登記の場合には、登録免許税などの実費も含めて20万円前後になるケースが多いかと思います。
詳しくは各事務所にお問い合わせいただくのが良いかと思います。
相談は連絡がとりやすい事務所に
手続きを依頼する場合には、途中で司法書士事務所と連絡を取りながら進めていくことになりますので、やはり連絡がとりやすい事務所にした方が無難です。
最近では、LINEで連絡が取れるような事務所もありますので、そういった事務所を探してみてはいかがでしょうか。
ちゃっと相続を運営する太田合同事務所もLINEでの連絡やオンライン面談も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
【まとめ】お盆前に準備しておきたい3つのこと
家族に話す前にできる『たった3つのステップ』
- 遺言書の有無の確認
- 法定相続人の把握
- 相続資産の把握
相続手続きは、ほとんどの人が初めての経験です。
その時はあまりよく考えず、いわれるがままに手続きに応じてしまったけど、後々よく考えてみたら本当にあれでよかったんだろうか?というモヤモヤが残らないようにしっかりと事前準備を行うようにしましょう。
ちゃっと相続は、豊橋、豊川、湖西エリアを専門にしている司法書士事務所が運営する相続専門相談窓口です。気軽な相続の相談先として、ご利用ください。

TEL 0532-62-5034
受付時間9:00~18:00
(土日祝日は要事前予約)